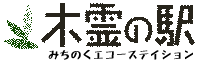 |
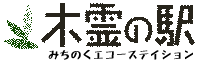 |
温暖化と雪エルニーニョ現象と積雪の減少盛岡気象台のデータ1923(大12)〜1994(平6)の積雪量及び長期積雪期間をグラフ化しエルニーニョ現象発生の年をそれに印したところ、両方とも大きな影響を受けていたことが分かった(中野1998)。 1923年(大12)と1994(平6)を比べると積雪期間は40~50日現代が少なくなっていることが分かった。1960年代に比べ1990年代は大幅に積雪量が減少し、積雪期間が少なく、融雪の早いことがうかがえる。岩手県安家川における調査でも河川水位の減、水温の上昇が認められる。
保水力の優れた森林と質の高い森林 〈積雪と水質、水量の研究報告から〉古い漁師のお話を伺うと、雪の多い年はコンブ、ワカメが豊漁であると口を揃えて言う(ウニ、アワビも増える)。雪の多い年は河川の水が多くなり、夏場の河川の水量も安定し水温も低いため、窒素を含んだ溶存酸素濃度の高い水が海に流入し、沿岸海水の高栄養化、温暖化を防ぎ水温を安定させるものと推測される。 森林の降雪量は表面貯水(雪)と地下貯水(氷や地下水)となる、積雪は多雪地帯において、年降水量の40〜50%を占めると報告されている。 川を流れる水の量の半分、特に夏場の河川水の多くを補う。 〈森林に蓄積される雪の必要性〉河川の水量は山地地下水がその量を大きく左右する。積雪を保ち、残雪の期間を長めることにより水資源の確保につながる。
〈保水力の高い森林とは〉最近「壮齡林からは水の供給が少なくなる」「森林は水の消費者」、など言われているが、優れた森林は間違いなく水源涵養機能が高い。
環境的に優れた森林・混交林優れた森林とは以上の機能を有するほか、生物の多様性をそれぞれ支える針・広葉樹が環境上適度に混交した森が良いと考えられる。 針葉樹と広葉樹の保水力の違いについては諸説から次のように考える針葉樹、広葉樹の適地は種類や成育環境によって違いがある(温度、乾、湿度、高、低山、土質など)、例えば天然林のブナ林とカラマツ林などを比較することは適当ではない。 人工林の場合、結果的に適地適木が無視され、広葉樹大径木林を伐採、若齢針葉樹人工一斉造林に変わった時、流出する水量が減じる森林が現れたことは現実であった。 しかしブナ林とスギやカラマツ林が同じ100年の林齡である場合の比較は、現在例になる森林が無いため推測の域を出ないが、針葉樹林が広葉樹林より保水力が劣るとは学術上の報告も無く、私40年山仕事の経験上も考え難い。 |
みちのくエコーステイション木霊の駅へのご意見、お問い合わせは・・・
|