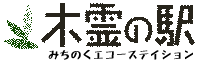 |
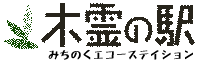 |
森林と環境―磯焼けパターン
磯焼けから海中林 成立のパターン 1 「サンゴモ平原」による岩礁の占有。サンゴモ科紅藻(無、有節サンゴ又は石灰藻と言う)「エゾイシゴロモ」、「エゾシコロ」などの特性。 ア) ウニ、アワビなどの植食動物の摂食に強い、表面剥離し易いため他の藻類が付着し難い。 エゾイシゴロモはジブロモメタン(揮発性ハロメタンの一種)を常時分泌している(生態相関物質と呼ぶ)。この成分はウニ、アワビの幼生を短時間で着底、変態誘起(Morse et al.1979)させるため、サンゴモ平原はウニだらけになることがあり、その摂食圧が続けば数十年磯焼けが続くことがある。 このような一面においてサンゴ藻は、ウニ、アワビにとって、重要な存在とも言えるが、ウニ、アワビの食料となる海中造林を造成することが重要なため、コンブなどの若芽を摂食させないためにウニを採取移動させ、海中造林の生成をを成功させた例も多い。 2 次の遷移段階サンゴモ平原には次に一年生海藻が発生する。 付着珪藻ヒトエグサ(ヒトエグサ科)の仲間やアナアオサ(アオサ科)等の発生は、摂食障害およびウニ、アワビなどの着底変態阻害物質(化学的防御効果を表す)を出し、植食動物の摂食圧をやわらげる。エゾヤハヂ(アミジグサ科)はケカジ草(凶作草)と呼ばれ(重茂周辺)多量のジテルペンを発し、ウニ、アワビを追い払ってしまう、この状態を漁師は「磯焼け」と呼ぶこともある。
3 海中林の形成小型多年生海藻の発生が遷移の進行を促進し、エゾイシゴロモの発生する温度より5℃位の低温でコンブ属藻類が発生する。コンブ科は低水温高栄養の条件下で発生する。 (水温が高く、低栄養下の場合でも一年生大型藻ホンダワラ科の藻は発生する。) 「海中林」を構成するコンブ科アラメは亜熱帯〜亜寒帯にかけての重要な海藻類でその成熟に2年を要し、平均寿命は満6年である(谷口ほか1991.1993)。
|
みちのくエコーステイション木霊の駅へのご意見、お問い合わせは・・・
|