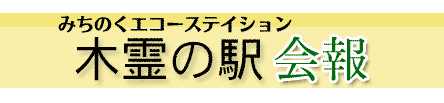
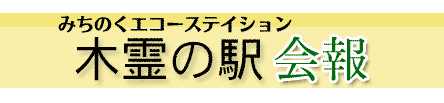
| スノーシューハイク。万澤安央 | 空飛ぶ樹木。高橋 理 |
| お告げの解答。葛巻佑二 お告げの質問。竹中啓子 |
虫さんのお話。後藤純子 |
| もし地球の歴史が1年だったら 川村晃寛 |
里山林の活用 吉村文彦 |
| 森は尽きないエネルギー9 中野雅幸 |
編集後記とナダレに注意 川村冬子 |
| 特別寄稿 里山林を活用することは自然を保全することである 吉村 文彦 (連載その2 前号より続く) 里山林という自然を保全するとは? 1)里山林(アカマツ林)の登場 昔、人は生活するために炭や薪や柴などエネルギー源を集落近辺の原生林で調達した。住居や神社仏閣を造るためにも膨大な量の材木を伐採している。生活用具の材料の採取も原生林であった。食糧生産には農地に肥料を施すが、落葉や刈敷も当然のことながら集落に近い林から得ていた。このような原生林の活用が人口増と共に激しさを増し原生林の再生能を超えた。終いには原生林という生態系から新しい里山林という生態系を創出するのである。いつ頃からアカマツ林が、今は全国的にはマツノザイセンチュウの害で減少しているが、日本列島にこれほどの密度で見られたのであろうか。花粉分析によると、アカマツ林は縄文時代には瀬戸内沿岸にのみ存在していた(安田喜憲 1998 森と文明の物語 ちくま新書)。本州、四国、九州でアカマツ林が増えた時期は500年頃からである(塚田松雄 1974 花粉は語る 岩波新書)がその急増期は鎌倉時代以降(1200年)で、東北北部へのアカマツ林の拡大は江戸時代後半から明治の始め以降に見られる(安田喜憲 1980 環境考古学事始 NHKブックス)。 2)里山林の崩壊 1955年に始まる高度経済成長によって私達の生活は「豊かに」も「便利に」もなった。家庭用燃料が薪炭から化石系に変化し炭の生産量がピークを過ぎた年も1955年であるが、これは里山林の活用の低下を招いた。その後、主たる産業が第3次産業に移行するにつれ里山林の放置がますます進行し、アカマツ林の構成樹種に変化が現れアカマツ優先が崩れた。うっそうと植物が茂り、緑豊かに見えるが植物の多様な生育環境が奪われ、多くの植物が姿を消しつつある。マツタケもその仲間の一つである。生物の多様性の価値を否定する人はいないが、「アカマツ林が極相林に変わってもいいじゃないか!」とか「樹を伐らなければ緑豊かになるのだから!」と単純に考える人が多く、「再び、人による森林の破壊が進行していて、里山林の植物が絶え、そのために植物を訪れる昆虫が絶え、それを餌とする鳥類に影響が及び、やがて自然はどうなるのか」と考える人は少ない。このことは、原生林の人為的な攪乱で登場し、しかも1500年という長期に渡って人が維持し続けた、だからこそ、里山林という生態系に適応した様々な生物を、たった45年間で葬り去ろうとすることであり、生物の多様性が保証されるべき自然を否定する行為ではないか。 里山林を保全するということは、その成立過程を見るならば、林を活用すること以外に道はないのではないか。 里山林の保全には林業活動が必要 1)林業技術が無くなる 森林保護や環境保全が声高に叫ばれているが、20世紀型の経済効率第一で解決しようとすると取り残されるように思えてならないし、また自然保護運動にも色々あって森林の健全な成長に障害となる運動もある。持続的利用とか持続的発展とか生物の多様性の維持とか言葉だけが氾濫している。どうしたら里山林を持続的に利用していけるのか、どこにもその提案がない。保護林を作ったり保護地域を作っても里山林の生物の多様性は守れない。森林は誰が守るのか、その資金はどうするのか未だに国民的合意はない。里山林という環境は私達の生活に大変大きな重要な機能を持っていることは明らかである。里山林という自然は、持ち主の物ではあるけれど、同時に持ち主の物ではない。私達の生活に密接な関係のある自然である。社会の共通財産であると考えることができる。道路が崩れたら補修するように里山林も補修するのである。営林署の林業技術者はその統廃合やらリストラでなくなってしまった。各地域の森林組合が抱えている林業技術者も高齢化し10年も経つと林業技術が廃れる恐れが出ている。森林ボランティアで国土の70%近くある森林を守れると本気で考えている人はいるまい。当然のことである。 2)再生可能な資源としての森林を活用 新しい林業を起こすしかないのではないか。森林は、建築用材の生産主体の場から持続可能な資源の生産の場であると位置づけを変える必要がある。里山林を保全するためにはその資源を活用する以外に方法はない。水を守るために神奈川県や福岡県や愛知県豊田市(高知県も)では水道代の一部を流域の森林保全へ還元している。長野県では森林育成に公的資金を投入するというように地方自治体独自の動きも出てきた。里山林の持続的活用を進め、林業を活性化するには森林の新しい利用法を作り出す必要がある。未だ課題のある技術もあるが少し挙げてみよう。 ①里山林を手入れして健全に維持し、アカマツ林でマツタケを栽培、ミズナラ林でホンシメジを栽培、カラマツ林でハナイグチやカラマツベニハナイグチなど食用きのこを栽培する。 ②木炭の新機能に注目した利用法の拡大 ③ペレットやチップを利用した暖房システムを導入 ④粗朶沈床法や木工沈床法など伝統的な河川改修法や法面づくりの復活 ⑤木質発電(コジェネレーション=発電と熱発生)による地域分散型の発電システムの導入 ⑥里山林(人工林)の手入れ時に発生する材や落葉落枝や腐植質、家庭や事業所から出る生ゴミと畜産廃棄物の糞尿を混合、破砕スラリー化し嫌気的に発酵、メタンガスを発生させる。メタンを触媒法で水素に変換し水素電池(コジェネ)の原料にする。残渣は有機堆肥にする。 ⑦植物資源のセルロース(材)を強力に分解するセルラーゼを産生するキノコを探索(現在のものは小動物等の分解物を分解している)。それを利用してグルコースを産生。また、セルロースやリグニンを超臨界法で分解、グルコースを作る。メタノールやエタノールを生産する。 (おわり) 吉村 文彦(よしむら ふみひこ)さん 1940年京都府生まれ。京都大学農学博士。 1990年に京都大学を退官、岩手県岩泉まつたけ研究所所長として着任。 今年3月岩泉での10年間の研究をまとめた「岩泉式まつたけ山のつくり方」を著述。 中野事務局長がまつたけ研究所を訪問した際、投稿をいただきました。 |
| 森は尽きないエネルギー パート9 アサとカヤとヨシと言えば カヤぶき屋根は垂木(たるき・竹や木材等を組む)の上にカヤ(すすき)アシ(よし)アサ(麻)を敷く。そのほか米ワラを使っている地方もある。 アシは"悪し"とも書くため"ヨシ(良し)"と呼ぶらしい。その芯は中空、水の中に生えるためだろう。その割に強く、束ねて船になるらしい。カヤは似ているがスポンジ状の芯がある。麻は強いので雪などで力のかかる軒(のき)部分に使う。岩手ではおよそこの3種を使っている。 麻は大麻のことで、今は法律で栽培禁止、生えていると保健所が来て引っこ抜く。麻の繊維は麻布、麻縄の原料、昔は無くてはならないもの。だが悪い奴が現れてその煙りを吸ったもんだから使えなくなった。 世界の森林減少や環境の破壊は、戦争や際限の無い消費文明が引き起こした。これはやっぱり"悪い奴"なのだ。アフガンで思った。援助とはまず欧米のシロモノではなく二〇年前のアフガンの自給的な文化を取り戻すことだ。彼等は尽きない豊かな暮らしを持っていたのだから。(中野雅幸) |
編集後記:新年号を出すつもりが、気がつけば立春。 "つもり"と「お告げ」は必ずしも一致しないのであります・・・。N編集長と皆さんのおかげで原稿を載せきれないほどたくさん頂いています。次号は早く出せるかな〜。(木霊のお告げ次第だよ!)/先月八幡平の源太ヶ岳で雪崩遭難事故がありました。川村家が毎春タケノコ採りに行く山です。6月に山頂直下に残る雪田をオシリで滑り降りた(と言うよりコケて落ちていった)ことがあります。心に残る滑り心地でしたが、あそこで雪崩が発生したのだ、思ったら寒くなりました。/雪崩は斜面に降り積もった雪が自重に耐えられずに落ちていく訳ですが、発生のメカニズムは複雑かつ微妙で、完全な予測は非常に難しいようです。積もった雪が時間とともに変態する過程(例:新雪がいわゆるしまり雪に変化するのも「雪の変態」)で、気温、湿度、雪自体の温度などの条件が絡み合って、雪の結晶どうしの結合が弱い「弱層」を形成します。その弱層の上に載った雪が、何かの刺激を受けて滑り落ちていくのが雪崩。/ある斜面での雪崩の危険度を予測するのに、「弱層テスト」というのがあります。雪を掘って円柱状の雪の柱を作り、それを手で引いて円盤状に切れる部分があるかどうかを調べるものです。切れる部分が弱層で、弱い力で切れればそれだけ危険度が高い。/雪崩を避けるために、日程、天候、ルートをよく勘案して行動するのは当たり前ですが、もし雪崩に巻き込まれてしまったら・・・。デブリ(なだれてたまった雪)に埋もれた遭難者は窒息、低体温、衝突による外傷などのダメージを受け、ことに窒息は数分を争う緊急事態。雪崩発生後15分以内に救出しなければまず生還しないとの報告があります。雪崩ビーコン(発信器)、スコップ、ゾンデ(探り棒)は雪崩遭難救助の三種の神器と言われます。/まず雪崩に遭わないこと。遭ってしまったら埋まらないこと。埋まってしまったら、すぐにもがいて脱出すること・探して掘り出すこと。これが出来ない人は危険な雪山へは行かないこと・・・。(FK) |